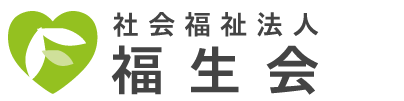福生会スタッフブログ
ハロウィンの由来を探る秋の夜長
こんにちは!福生会ヘルパーステーションの西脇です。
だんじりのお祭りも終わり、少しずつ秋の気配が感じられるようになってきましたね。最近では街中やテレビでハロウィンの飾りや特集をよく目にするようになりました。

皆さんは、ハロウィンについてどのくらいご存知でしょうか?私自身、「仮装をする行事」「カボチャの飾りがある」という程度の知識しかありませんでした。そこで今回は、この季節にぴったりのハロウィンについて少し調べてみました。
ハロウィンの起源は、なんと2000年以上前のケルト人の祭りにまで遡るそうです。古代ケルト人が信仰していたドルイド教では、11月1日が新年とされていました。年の変わり目である10月31日から11月1日にかけては、あの世とこの世の境界が薄くなり、霊が行き来すると考えられていたのです。
この時期に人々は収穫物や動物を捧げて新年を祝うとともに、悪い霊から身を守るために仮装をしたそうです。また、カボチャに顔を彫って灯りを灯す習慣は、悪い霊を追い払うための工夫だったとのこと。当時よく食べられていたカボチャが使われるようになったそうです。
現在、私たちの施設では幼稚園の園児たちが作ってくれた素敵なハロウィン作品を飾らせていただいています。かわいらしい作品に、訪れる方々も笑顔になっていらっしゃいます。

クリスマスやだんじりなど様々な季節の行事がありますが、秋の夜長に、こうした伝統行事の起源や歴史に思いを馳せるのも素敵なひとときではないでしょうか。皆さんも季節の移り変わりを感じながら、穏やかな秋の日々をお過ごしください。
カテゴリー:福生会スタッフブログ [2025-10-18]